今回はこんな悩みを解決していきます。
模試は、年に何回もあり、様々な団体がそれぞれ特有の模試を実施していますよね。
「どこの模試を受ければ良いのか。」「受け方と結果の見方」などを昨年まで、現役受験生だった私が解説していきます。
Contents
模試の重要性とは?

恐らくこの記事を見てくださるほとんどの学生の方が模試についてはよく理解していると思います。
ですが、○判定などの結果だけに注視しすぎていませんか?
模試の重要性の本質はそこではありません。
模試は「自分の苦手な範囲を理解する」ことが重要になってきます。
ただ、判定結果だけを見ているのはお金の無駄になるので絶対にNGです。
模試の正しい受け方と結果の見方について下記以降述べていきます。
模試の正しい受け方
模試を受験するのあたって重要なポイントを3つにまとめました。
- 模試を受けるまでにできる限りの勉強を済ませておこう。
- 模試の問題にチェックをつけておこう。
- 復習を怠らずにしよう。
基本的なことですが、できない受験生も多いので基本的なところから丁寧にしていきましょう。
1.模試を受けるまでにできる限りの勉強を済ませておこう。
まず模試は、1年を通して毎月のように実施されています。
なので、自分の受けたいタイミングで受けることが比較的自由に決めれます。
模試を1つの受験勉強の軸にして、模試を受けるまでにその時の自分の最大限の受験勉強を行ってください。
時々、模試を腕試しのようにぶっつけ本番で受ける受験生を拝見します。
ですが、模試は1回6000円以上するのが普通です。
6000円を有効的に使うために、受験勉強を1日1日コツコツ取り組んでみてください。
模試の年間スケジュールをみたい方は下記のリンクから!
2.模試にチェックをつけよう。
模試と受験本番で違うことは、問題を持ち帰るか否かにあります。
模試の大抵は、問題を持ち帰ることができます。
なので、模試中に答案にマークしながら同じ番号に、問題にもチェックを忘れずにしてください。
これは、次にも語るのですが、復習をより効果的にするためです。
模試中の緊張感と一度落ち着いて問題を見ると、見え方が変わります。
なので、模試中の自分の考えが分かるように、問題に印をつけるのは必須事項として覚えておいて下さい。
3.復習を怠らずにしよう。
模試で一番重要なのは、模試の結果でもなく事前の準備でもなく「復習」です。
それは、受験本番は、一発勝負。
それまで苦手範囲をできる限り減らすのが合格への近道です。
受験は長所を伸ばす勉強法より短所を無くし、平均値を上げる勉強法が功を奏します。
なので、本番形式でテストを受けれて、復習までできる模試は受験生にとってかなり重要なイベントなのです。
復讐のやり方が分からない受験生もいると思います。
- 模試の返却前に、自身の無い問題、答えられなかった問題の解き直し。
- 模試返却後、自分が間違った部分を解き直し。
- 各科目で、どの範囲が苦手かを分析。
- 苦手と分かった範囲を重点的に今後の勉強計画を立てる。
この手順を参考に復習をしてみて下さい。
模試の結果の見方
個人的に模試の結果で見て欲しい所は、2つだけです。
それは「各科目の問題の正誤」と「問題の平均正答率」です。
この2つを見ることで「自分がどこで間違ったのか。」&「他の受験者はどこで間違っているのか。」がはっきり理解できるからです。
ただ正誤率を見て一喜一憂するのではなく、自分の苦手範囲を洗い出して下さい。
その後、志望校の判定結果を見て、自分の現在の立ち位置がどの程度か確認して下さい。
模試の結果を見るのにおすすめなサービス!
「模試ナビ」をご存知ですか?
模試ナビは河合塾が運営している目標点の設定や模試の結果などを見ることができるサービスです。
過去の模試との成績比較もできるので、復習もしやすいのがおすすめです。
河合塾は、模試を多くしている予備校なので、学校で河合塾の模試を集団受験する高校も多いかなと思います。
そういった際やそれに限らず個人で受ける場合も「模試ナビ」を活用してみて下さい。
まとめ
今回は、受験生が受験期に受けずに道を通れない模試の重要性をまとめました。
模試はA判定のように、志望校に対する合格率が出るのでそちらに目が行きがちですが、本質はそこではありません。
- 模試を受けるまでにできる限りの勉強を済ませておこう。
- 模試の問題にチェックをつけておこう。
- 復習を怠らずにしよう。
この上記3つを参考にして、受験料6000円と自分をより成長するために模試を有効活用してみて下さい。
模試は、一つの軸であり通過点です。
なので、くれぐれも模試の判定に一喜一憂して、受験勉強の火が燃え尽きないようにして下さい。
本日はここまで。
じゃお疲れ様した!
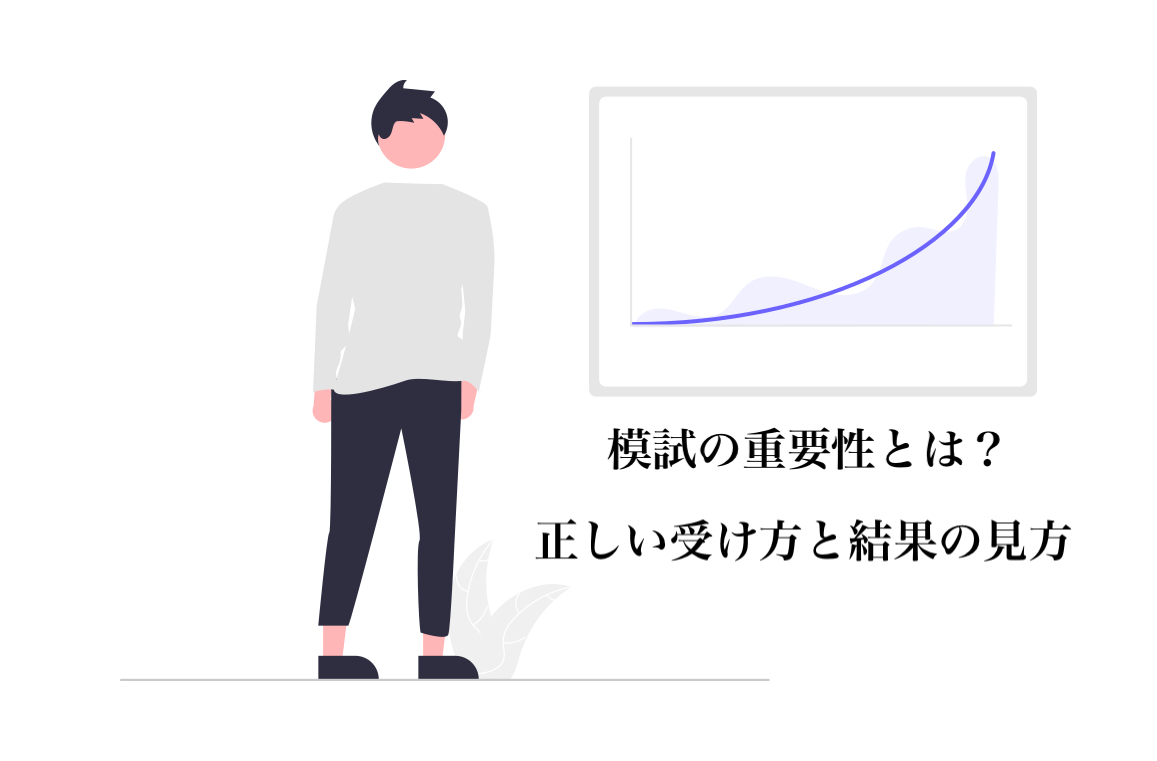



模試ってどれくらい重要で、受け方とか結果の見方とかあんまり分からん。